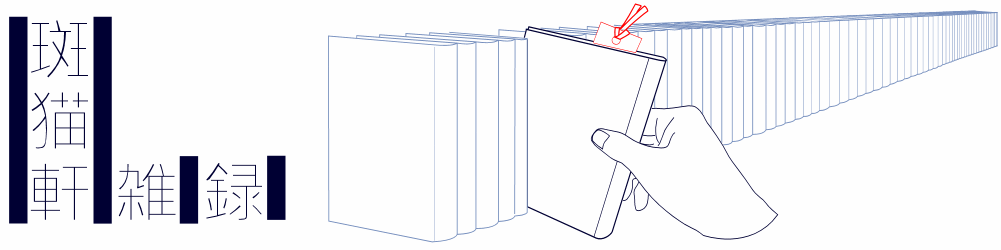鳥学大全 「鳥のビオソフィア 山階コレクションへの誘い」図録 東京大学出版会2008年 B5判 P631 プラスチックカバー少キズ 小口少キズ
編:秋篠宮文仁、西野嘉章
2008年、東京大学が創立百三十周年記念として開催した特別展示では、財団法人山階鳥類研究所の協力を得て、標本、図譜など274点が公開されました。
本書はその際に刊行された図録…なのですが、簡単な解説を添えたただのカタログのようなものだと思ってはいけません。
電話帳くらい分厚い631ページ。その大半を占めるのは展示品の図版ではなく、多数の執筆陣によるさまざまな論説。目を瞠るほどの労作です。
この『鳥学大全』、「鳥学」と書いて「とりがく」と読むのだと、編者の一人である秋篠宮文仁殿下(山階鳥類研究所総裁/東京大学総合博物館特任研究員)は巻頭で述べています。
ここでひとつ断っておかなければいけないのは、本書の題名が「ちょうがく大全」ではなく「とりがく大全」だといういうことである。「ちょうがく」は近年あまり使われなくなっているが、以前は鳥についての研究分野である鳥類学(Ornithology)と同義でふつうに用いられていた言葉である。そして、この言葉からは自然科学、なかでも生物学を中心とした野鳥の研究領域との印象を強く受ける。しかし、鳥についての研究には、鶏や家禽も含まれるし生物学に特化したもののみでもない。
たとえば、民族鳥類学(Etynoornithorogy)という分野がある。民族生物学の一領域だが…〈略〉…
また、芸術の中にも鳥は題材として扱われている。日本の花鳥画と西洋の博物画がどのように違うのかを考えてみるのもよいだろうし、音楽のなかで鳥がどのように表現されているかを調べてみるのもおもしろい。さらに芸術とはいえないかもしれないが、造形物としての鳥が果たした役割もある。…〈略〉…
これらすべての事象を鳥学として表現できないかと考えたとき、編者等には自然と本書の発想が出てきた。つまり、鳥類学である「ちょうがく」ではなく鳥の学問である「とりがく」を集積しようと。
自然科学の一分野としての「ちょうがく」ではなく、あくまで“鳥”についての全般的な学問「とりがく」……本書にこめられたその意図は目次を眺めてみれば一目瞭然。
各章には「総論」「語源・神話・伝承」「文化誌」「図譜・美術」「驚異」「形態」「生態」「保全活動」……といったタイトルが並び、それぞれの項目ごとに数篇の論文・評論が掲載。つまりはさまざまな分野の視点から“鳥”をめぐる知を網羅しよういう試み。
こうした知的野心にはどこかしら19世紀風の博物学志向と共通する部分がありそうですが、「博物学」といえば20世紀のある時期から、往々にして正統な研究とみなされない傾向にあった分野。「殿様博物学」「殿様生物学」という言葉もあるとおり、金と暇を持て余した人の道楽、とアカデミズムの側からみればそんなふうに映ったのでしょう。
とはいえ、それをいうならばそもそも、この企画の大元である山階鳥類研究所とそのコレクション自体がかつては「殿様鳥類学」のそしりを免れなかったわけで。そのことは本書のもう一人の編者・西野嘉章氏(東京大学総合研究博物館館長/財団法人山階鳥類研究所副所長)の緒言からも伺うことができます。
鳥の剥製標本は美しい。このことが、東京大学において鳥の剥製標本を積極的に蒐集することを妨げた理由の一つであるかもしれない。かなり長い間、科学的であることと美術的であることが背反することであるように考える大学人が少なくなかったように思える。美しい剥製標本を蒐集するのは、趣味人のすることであって、科学者のすることではないという、狭量な心の大学人が大勢を占めていた時代、それに逆らって標本を蒐集するのが容易でなかったことは理解できる。
そうした時代背景にあっても、財団法人山階鳥類研究所は標本を蒐集・整理・保存することを怠ることはなかった。…〈略〉…
東京大学から見た今回の特別展示の意義は、そうした財団法人山階鳥類研究所の努力に敬意を払いつつ、新たな協働の道を模索することではないかと思う。『鳥学大全』という大それた本の出版を企画したのも、鳥学において東京大学はいまだに揺籃期にあるという謙虚な認識のもとに、新たな一歩を踏み出す決意を示そうとしたことにある。
とにかくアカデミズムの本流とは認められてこなかった知性をも積極的に取り入れようという姿勢。もちろんこの認識が大学関係者の総意であるかどうかは当方にはわかりかねますが、何しろ面白そうな試みではありませんか。
引用した文の最後に「決意」という言葉が出てきますが、早速それが表われているように思えるのが本書冒頭の「総論」の章。
というのも、編者2人が寄稿するこの最初の章に収録されている第三の人物が、なんとあの荒俣宏氏。
(ここで「なんとあの」という枕詞をつけたくなる、荒俣氏のイメージや立場がそのまま、現在の“博物学”に対する扱いを示してもいるわけですが。そういう意味でも氏が現代日本を代表する博物学者であるということはいえるかもしれません。)
たしかに本書が「21世紀の博物学」を目論んでいるとすればこれ以上ない人選ではありますが、東京大学創立百三十年の企画展という側面を考慮すれば、大学関係者でなく在野の「知の巨人」をここに抜擢したというのは、ある意味で英断ともいえるのではないでしょうか。
* *
さて、その荒俣氏の論説、「鳥類図譜の系譜」。
本書の目次をもう一度見返してみれば「図譜・美術」という章も設けられており、タイトルから判断するならば、そこに収められてもよさそうな気もしますが、もちろんこの博覧強記の人の文章が一つのジャンルにとどまっているはずもありません。
クロマニヨン人の洞窟画から語り起こされる人間と動物の関わりは、ギリシャ・ローマ時代の思想・学問、エジプトの宗教観、プリニウスの博物誌へと次々に接続され、さらにはグーテンベルクの活版印刷や航海術というメディア史、技術史上の革新をも射程にとらえつつ、ソフト・ハード両面から図譜の歴史を語ります。
古代・中世・近世と、なかなか一貫した流れで語ることの難しそうな“博物学の歴史”を「支配」「所有」という動機から解釈してみせるあたりもさすがの見識。学問分野の垣根を越えた脱領域的ロジックは本書の意図を十二分に体現したものといえます。
「在野」でこそないものの、長い間アカデミズムの中で異端視されてきた、という点では、漢字研究の白川静の名前があるのもやはり意義のあること。
この企画の2年前、2006年に既にこの世を去っている白川博士の遺した仕事の中から、本書では「鳥占と古代文字」という文章を掲載しています。
ここで主に取り上げられるのは鳥の象形から派生した「隹」という文字。この字が古くから肯定的な意味を付与する接続詞(漢文の読み下しでは『これ』や『と』などと読まれます。英語でいえばandやthen,に近いニュアンスでしょうか?)として幅広い意味で用いられていたことを、甲骨文・金文に見られる語法の例にまで遡って説きます。さらに「隹」には“神意”“神託”を示す字義があったと述べ、鳥を神意の媒介者とする古代社会の信仰やそれに関連した祭祀の有様を、「隹」から派生したさまざまな文字(『唯』『雖』『雇』など)の本来の字義を手がかりに読み解いてゆくのです。
たとえば神への祝詞や盟誓を収める器を示す形象字「口」を「隹」に添えた「唯」には神の応諾を得る「しかり(然り)」の意味がある一方で、ここに神意を妨げる「虫」(呪法として有名な『蠱』ですね)を加えると逆説を意味する「雖(いえども)」になる、といった例や、神託を得るために行う狩りに用いられる鳥が「鷹」である、など興味深い話ばかり。
その他、店主が個人的に面白く読んだものをいくつか挙げると。
●夏・殷・周・(秦)・漢という中国古代王朝を金・水・木・(閏)・火という五行説に当てはめる五徳終始説と孔子に関する伝説から四神獣の由来を読み解く「南方の守神 朱雀の誕生」(平勢隆郎)
●キリスト教の宗教画に描かれたさまざまな鳥の象徴性の変遷を辿る「中世ヨーロッパにおける鳥の表象」(金沢百枝)
●江戸時代の将軍たちが鷹狩りの獲物を各藩大名に下賜した記録を丹念に辿り、その政治的な意味合いを読み解く「将軍の鷹狩りと大名―「御鷹之鳥」をめぐる諸儀礼」(大友一雄)
●19世紀に美しい鳥類図譜を数多く残したジョン・グールドの、構図の変遷や当時の時代背景などを解説した「「鳥の人」ジョン・グールドと『ハチドリ科鳥類図譜』」(黒田清子)
●鳥の恐竜起源説に基づき、行動、呼吸、飛行などがどのように進化を遂げたか、その段階を推測する「恐竜はいつどのようにして鳥になったのか」(真鍋真)
●クジャクの求愛行動において、羽の模様や体格、しぐさ、鳴き声など、何が“モテる”個体を決定するのかという観察や、他の鳥類の行動にも言及し、さまざまなアピール行動が進化の中でどのような意味を持ってきたのかを考察する「鳥のディスプレイ―クジャクの求愛から擬傷まで」(長谷川寿一)
……とにかく紹介しきれないほど興味深い「鳥学」研究の集積。
当店サイトの商品説明に目次のほぼ全文を掲載しております。
さて、皆さんはどんなテーマに興味を持つのでしょうか。