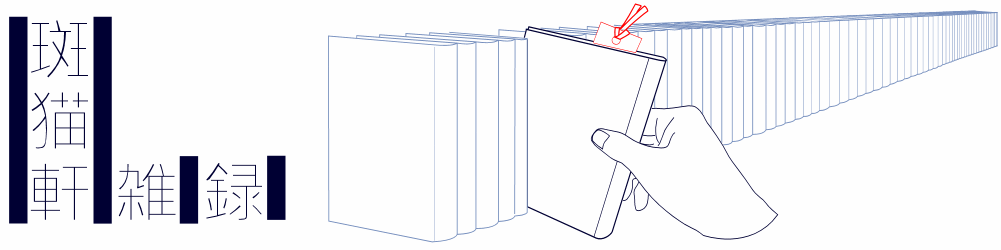新泉奇談 泉鏡花 千部限定版 角川書店
昭和30年初版 四六判 P290 函ヤケ、天イタミ、時代シミ 元パラ上部少イタミ、袖折れ跡
作家の生前には世に知られることなく、没後に原稿が発見された作品――。
こういうとき、当然出てきてしかるべきなのが、その真贋をめぐる葛藤や議論。
百家争鳴といいますか、一家言持つ人たちの声々姦しく、かえって真相はますます藪の中に……、というのは、関係者や読者の思い入れが強い作家であるほど起こりがちな事態なのかもしれません。
たとえば泉鏡花の生前未発表小説『新泉奇談』が発見された際の状況がまさにそのようなもので……。
昭和30年に角川書店から初めて刊行された『新泉奇談』には、作品のほかに、3人の関係者による解説的な文章が収められています。
後輩作家として鏡花の知遇を得ていた里見弴。
鏡花の弟子であった寺木定芳。
鏡花研究の第一人者村松定孝。
そこには本書刊行までのさまざまな経緯とともに、この作品の真偽をめぐる各々の立場からの所見、その根拠とした材料などが述べられてもいるのですが、後世の目から見れば、この時点で『新泉奇談』の真偽問題にケリがついたといえるわけではありませんでした。
本書刊行後もさまざまな識者によって議論され、真作説派・贋作説派どちらからも、いくつかの新資料や新証言が示された末、一応の決着らしきものを見出せるのは昭和47年頃。
本書刊行から15年以上、原稿発見からじつに20年以上の歳月を要した議論。その紆余曲折の経緯について、上記3篇の解説文および、その後の論考数篇を参考にしつつ辿ってみる、というのが今回のブログ記事の内容です。
※ ※ ※
コトの発端は昭和21年。鏡花の弟子として生存する最後の一人であった寺木のもとに、「A新聞のK氏」という人物が訪問してきたところから話は始まります。
このときK氏を寺木のもとに差し向けた紹介者は作家の久保田万太郎。
その来意は、「関西で鏡花先生の未発表小説の原稿三百枚ばかりが売物にでて、本社へ売り込みにきてゐる、其の真偽を決定して貰ひたい」というもので、「その原稿の初ページ二三枚の写真版をみせられた」と寺木は回想しています。いうまでもなくこれが後に物議を醸す『新泉奇談』の原稿でした。
寺木の見立てでは、原稿の字体はもとより、誤字を墨黒々と塗りつぶして書き直す独得の書き方の作法まで、まさしく鏡花の真筆。
しかし万が一にも間違いがあってはならない鑑定依頼、念のために鏡花未亡人にも写真を見てもらい「確にあるじの筆躍に相違ない」という返答を得て、K氏に伝え写真版を返却してひとまず一件は片付いたのですが。
その一年後、寺木はまたしても『新泉奇談』原稿の鑑定を依頼されることになりました。
ただし、持ち込んできたのはK氏ではなく、小島政次郎紹介の京都和敬書店主人、“関氏”こと関逸雄。くだんの原稿を苦心の末に入手した関氏は、作品の出版を検討しており、ついては寺木だけでなく、鏡花の友人であった人々でこれを判定してほしいとのこと。
原稿二三枚分の写真を渡された一年前とは異なり、このとき寺木は関氏持参の生原稿を目にし、また、寺木の呼びかけで鑑定に加わった里見弴・久保田万太郎・三宅正太郎・鏑木清方も、後日送られてきた三百枚近くの原稿すべてのコピーを回覧。
さらにもう一つ、鑑定者たちの前に示された注目すべき資料は、関氏の入手した原稿に添えられていた鏡花自筆の手紙でした。
日付は明治三十五年六月二十六日、宛名は当時大阪毎日新聞学芸部長であった菊地幽芳。
文面には連載二十回分の原稿を送付した挨拶、原稿料は三十回分を先に渡してほしいという申し出、当時鏡花が編集に携わっていた雑誌「新小説」に幽芳が寄稿した作品の経過、といった内容が記されています。
つまりは、おそらく『新泉奇談』原稿はこの手紙とともに幽芳のもとに送られたのだろうという、およその出所が知れる重要な手掛り。
とにもかくにも、ここにおいて寺木はじめ複数の鏡花関係者たちが初めて全貌を目にすることとなった『新泉奇談』。しかしながら、この小説は彼らを大いに戸惑わせることになったのです。
このとき鑑定人の一人であった里見弴の本書解説には次のような一節がみられます。
さて玆に肇めて世に現るゝところの『新泉奇談』なる小説であるが、私一個として、およそこれくらゐ判斷に苦しむ事實に直面したことは、未嘗て覺えがないと言つてもよからう。――勿論、果して泉鏡花の筆になつた作か、否か、にしてである。
里見と寺方の証言をもとに、鑑定のポイントとなった部分を要約すると以下の通り。
・まず、その筆跡は鏡花のものに間違いない、という判断はこの度も全員の見解が一致。
・小説の舞台が千葉県である、という他の鏡花作品には見られない設定に当初は不審があったが、「(鏡花の師である)紅葉先生が御病気で犬吠埼に転地され、そこへ再三鏡花先生が見舞いに行つたことがあるから、その時の見聞がこの小説になつたのだらう」という、鏡花未亡人の言葉によって解決。
この辺りは“『新泉奇談』真作説”を補強する材料。
一方、“贋作説”に傾きそうな材料は、原稿そのものよりも、もっぱら周辺の状況に不審が多いという点にありました。
・鏡花の作品および原稿については、昭和15~17年にかけて岩波書店から全集が刊行される際に上記鑑定人たちも編集に関わって、寺木いわく「一雑文すら見落とさない」意向のもと徹底的に調べつくしたはず。実際、発表誌不明・原稿紛失という手掛りのない作品も標題だけは全集に収録されている。
・それでなくとも、自らの原稿を必ず手元に取り戻して保管するのを常としていた鏡花。自筆年譜には原稿の一部を散逸した作品の標題が記される例があるほど自ら書いたものに固執しており、たとえ上記のごとく原稿を紛失することは稀にあるにせよ、原稿の一部どころか全篇を手放したきりになっている『新泉奇談』について何の記録もなく、口の端にのぼるのを聞いた者さえ鑑定人の中にはいない、ということがありえるのか。
・そもそも手紙の日付である明治三十五年頃といえば、すでに鏡花の文名は確固たる地位にあり、その長篇小説が掲載されていない、つまりはボツになるとは考えにくい。
いや、仮にこうした不自然な点を「そういうこともある」と片付けることができたとしても、里見にとっては心情的にどうにも受け入れ難かったであろう事実がもう一つ。
最後に、作品の出来榮である。未亡人や出版元に對しては、少々言ひにくい次第だが、假に泉鏡花の眞筆としてこれに臨む場合、忌憚なき私の評價を以つてすれば、代作、或は失敗にちかい作品と考へられる。
《略》
繰り返して言ふが、筆跡に間違はなささうに思はれる。構想、布置、行文、登場人物竝に彼等の行動に對する好みや正義感など、すべて十二分に鏡花的である。《略》出来は悪いにしても、はつきり先生の作だと断じたいのは山々なのだが、数千言を来たつた上述諸般の事情に照すとき、いかにも不可解な點が多すぎる。
鏡花の没後十年以上経って現れた、“幻の作品”となるはずだったその小説は、あろうことか“失敗にちかい作品”、つまりは駄作だったのです。
里見のように生前の鏡花と親しく交わり、その文才を愛した者にしてみれば、これを鏡花の作品と認めることに躊躇が生れても無理はありません。
こうなると、なまじ筆跡が本物らしいことや、駄作とはいいながらもところどころには才気迸る箇所も見えることが、かえって複雑でもあり。
いっそこれが箸にも棒にもかからぬ偽物であってくれれば……とまで里見が考えたかどうかはわかりませんが、結局のところ筆跡や文章は紛れもなく鏡花のもの、不審な周辺状況はあくまで“不審”であって可能性0%というわけではなし。
話は自然、落ち着くべきところに落ち着いて、『新泉奇談』は和敬書店から出版の運びとなります。
しかしながら。
冒頭で紹介した通り、『新泉奇談』は昭和30年に角川書店から初めて刊行された作品。
じつは和敬書店版の『新泉奇談』は、校正刷まで出来ていながら、版元の都合で頓挫してしまったのです。
こうして再び世に出ることなく埋もれようとしていた作品が、どのようにして日の目を見ることになったのか。刊行後どのような議論が識者たちの間で交わされたのか。そうして、『新泉奇談』の真贋はどんな形で決着したのか―。
この話は次回に続きます。