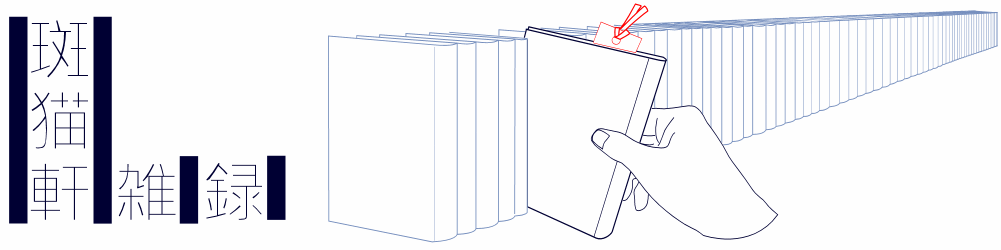『ヘスペルス あるいは四十五の犬の郵便日』(ジャン・パウル 訳:恒吉法海 九州大学出版会)1997年初版 A5判 P697 カバー少イタミ、クスミ 帯背ヤケ、イタミ 天少汚れ

ドイツ文学者だった作家・古井由吉は、かつて自ら翻訳したこともあるロベルト・ムージルの作品について、
・「作品の価値は高いと思いますが、凝縮度があまりにもはなはだしくて、言葉の能力を限界まで使っていますので、読むほうとしては、気力体力をよほどためて向かわないと、なかなか歯が立たない。」
・「疲れているときに読めといわれたら困る小説のひとつでしょう。」
と語り、その要因の一つとして、ドイツ語の持つ特性を挙げています。
ドイツ語のことはご存じの方も多いでしょうが、接続詞とか関係代名詞とかをつかってクローズをつぎつぎにつなげて、だいぶ長いセンテンスを組み立てることが可能です。重層的な構築の美をあらわす、という美的な欲求もあるのでしょうが、ひとつの文章の時間の内に、さまざまな時間や次元を込めたい、多様なものをひとつの時間の内に融合させたいという欲求が、ドイツ人及びドイツ語自身にはあるようです。(『ムージル 観念のエロス』より)
ムージルより百年あまりも古い時代の作家、ジャン・パウルの長大な小説『ヘスペルス あるいは四十五の犬の郵便日』を読む人の中にはもしかしたら、上記の言葉によく似た印象を持つ方もいらっしゃるかもしれません。
実際その作品には、じつに入り組んだ文法で書かれた長いセンテンスがいたるところに横たわっていて、翻訳者の苦心の跡は認めた上で、なお読みづらいという印象を拭えないのです。
たとえばそれはこんな具合。
ホーリオン ― アクセントは第一音節でなければならない ― あるいはセバスティアン ― 短縮してバスティアンともアイマン家の人々が呼ぶように ― あるいはヴィクトル ― 彼の父のホーリオン卿が呼ぶように(私は私の散文の韻律の要請に従ってその都度呼び方を変えるが) ― このホーリオンは牧師の一家にイタリア人トスタートを通じて、彼は一帯の人々にとってさまようアウエルバッハの旅館であり、聖リューネに向かっていたが、自分は金曜日に着くというささいな嘘を口頭で言わせていた。
もちろん、これはとりわけ読みづらい文章の一例ですし、こんなふうに前後の文脈を欠いた引用では、実際に作品を読むよりも読解が困難なのはたしかです。しかしそうした事情を差し引いても、『ヘスペルス』を初見でスラスラと読み下せる人はあまり多くはないだろうと思うのです。
なにしろ翻訳者のあとがきに
「『ヘスペルス』を読破した日本人は現在一桁の数であろうと思われますが、この翻訳で三桁に増えれば訳者冥利に尽きることです。」
と述べているくらいですから、いうなればこれも「気力体力をよほどためて向か」う必要のある作品といえるでしょう。
ところが、こうした“凝縮度のはなはだしい”、癖の強い文学作品には、読み進めるにつれて、その書き方の規則のようなもの、または論理の道筋のようなものがおぼろげに見えてきて、それらをひとたび受け入れた途端グイグイと作品世界に引き込まれてしまう、ということがあります。
そんなふうにドップリと、文体に象徴される作品の世界観に入り込むことで初めて感じ取れる叙情や切実さ、というものが、小説にはたしかにあるのかもしれません。現実的に醒めた意識で読んでしまえば不条理とも陳腐ともとられてしまうもろい叙情、安いたとえを用いるならば、夜の夢の中でだけ受け入れられうる切実さのようなものが。
一見複雑なその文体を受け入れてもらわなくては一切が陳腐に成り下がること。『ヘスペルス』がそういう作品だとは、作者ジャン・パウルも自覚していたようで、その序文にいくつかの「お願い」を挙げています。
たとえば、「あるいは四十五の犬の郵便日」という副題のついた『ヘスペルス』は、各章に「第一の犬の郵便日」「第二の犬の郵便日」といったタイトルがつけられているのですが、作者の最初の願いというのは、ここに仕掛けられた作者の意図を手早く知りたがらず、「第一章で説明し、釈明するまでは大目に見て欲しい」というもの。
さらに、「いつも章全体を読んで、中途半端に読まないこと」とも言い、批評家に対しては「その書評と銘打つパンフレットに手回し良く粗筋を印刷しないで、読者に一回きりしか体験出来ない若干の驚きを取っておいてほしいということ」と“お願い”しています。
翻訳にして600ページをゆうに超える小説をあらすじも説明しないまま「中途半端に読まないこと」などというのは現在の感覚からすればずいぶん不親切にも思えますが、この作品はたしかにそのように読まなくては面白くない類の小説かもしれません。
読者を遠ざけかねない「お願い」があるにもかかわらず、出版された1795年当時、この作品はドイツで大流行し、ジャン・パウルの名を一躍有名にしたといいます。
同じ年に『ヴィルヘルム・マイスター』を出したゲーテが、シラーに宛てた手紙の中にも
ところで目下のところ犬の郵便日が、教養ある人士が有り余る喝采を送っている作品だ。
と書いているとのこと。
だから是非読むべきだ、と言うつもりはまったくありませんが、あらすじの要約を禁じられた上でさしあたり紹介できることはあまり多くないのです。せいぜい上記のような事実と、あとは「お願い」とともに序文に記された、次のような著者の呼びかけをそのまま引用するくらいでしょうか。
来るがいい、疲れた魂よ、何か忘れたいことがあって、悲しい一日か、曇った一年、あるいは自分を侮辱する人間か、自分を愛する人間、あるいは枯れ落ちた青春か、苦しい生涯を忘れたい魂、それに現在が一つの傷であって、過去が一つの傷跡である、抑圧された精神よ、私の宵の明星にやって来て、そのささやかな微光を楽しむがいい(『ヘスペルス あるいは四十五日の犬の郵便日』序文より)